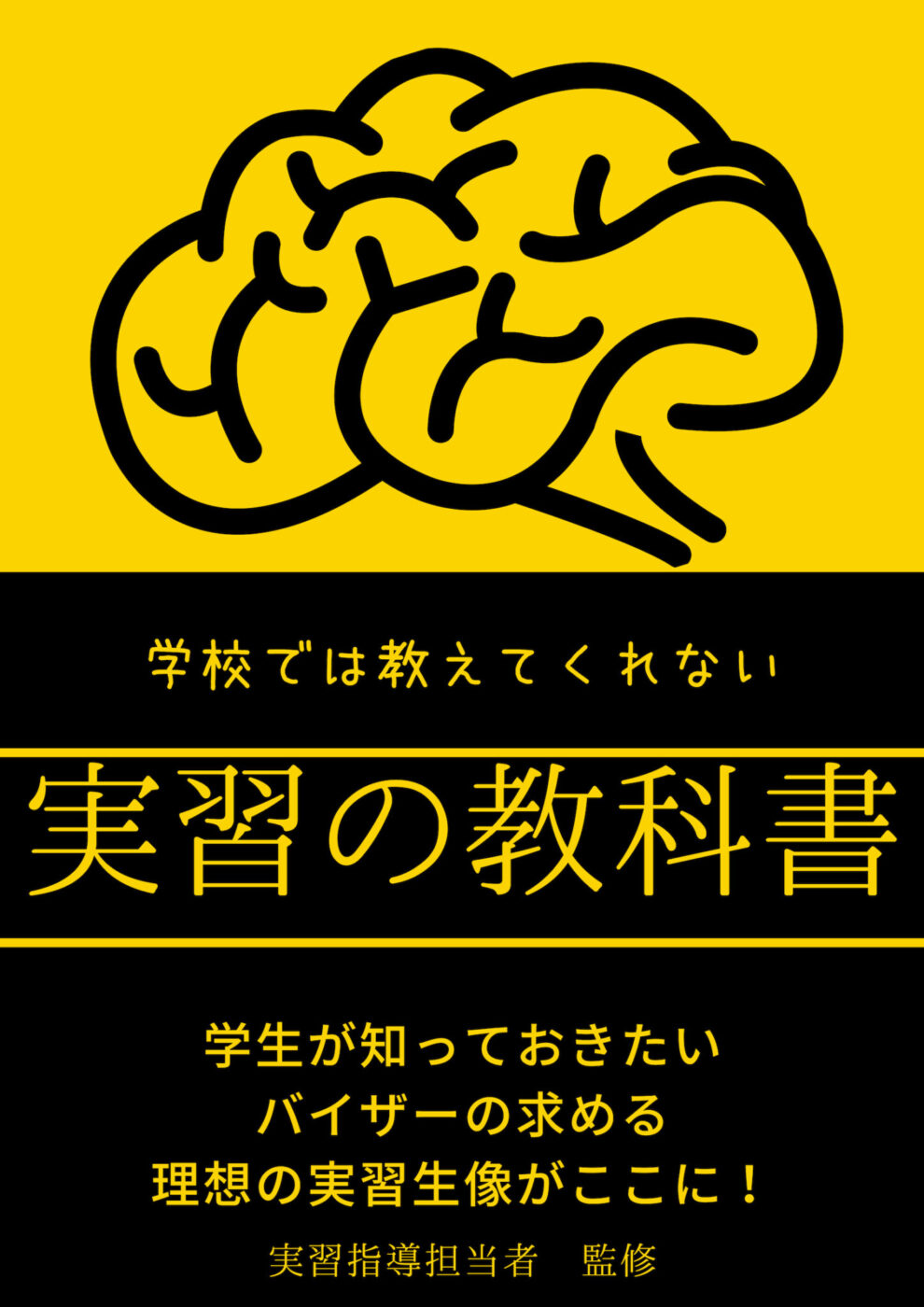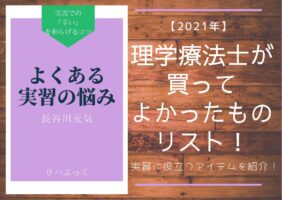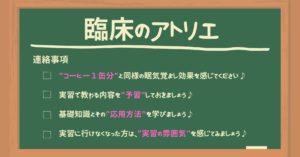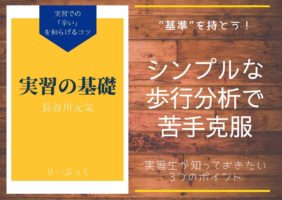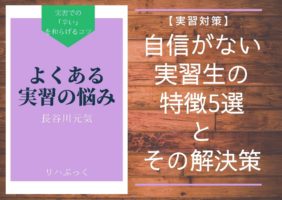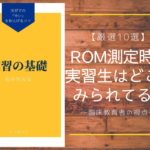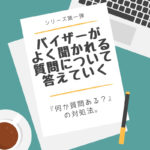よく取り上げられる『量』と『質』問題について
「量こそすべてでしょ!」
「いやいや、質でしょ!」

なんて論争がされているのをよく見かけますよね。
たしかに、どちらも捨てがたいものです。
考えれば考えるほど『量』も『質』も大切な気がしてきますよね。

『量』と『質』の論争は、これからの実習体系である”CCS(クリニカルクラークシップ)”においても注目されています。
これまでの実習では人によって「質の低い教育を大量にさせられる」ものであったため、国レベルで修正を求められました。
そんな中で採用されたCCSではどのようになったのか。
今回はそこにも触れていきます。
ということで、今回は学生さんが知っておきたい『量』と『質』論争の”結末”についてまとめていきます。

『量質転化の法則』とは
まず、『量質転化の法則』というものをご存知でしょうか?
『量質転化の法則』とは、その成り立ちからも想像できるように、「量を積み重ねることで、質的な変化をもたらす」という意味の法則です。
つまり、量なくして質は得られないというものが法則として成り立っているのです。
これはビジネス界や教育界においても有名な法則となっています。
ということで、この法則があるため『量』と『質』論争の”結末”は『量』であることがわかりましたね!
\\\\\結末/////
『量』の勝利!!!

【 量vs質 論の行方は?】
「量こそ全て!」
「いやいや、質でしょ!」
どちらが正しいのかという論争が良くされています。
しかし、両者はもともと対立するものではありません。
『量の多さが質の高さに繋がる』のです。
つまり量をこなさなければ、質は高められないのです。
— はせがわ🧭CCS(クリニカルクラークシップ) (@PTsupervisor) March 21, 2020
ん?
なんかあっけない結末となってしまいました??
そこに関しても触れていきますので、もう少し『量』の良さについて触れます。
『量』を求めたほうがよいことを学生さんにもわかりやすく例えると、
論文の精度を考えてみましょう。
以前、以下の記事でも触れたように、論文の信頼性が高くなるには”ある程度の症例数が重要”となります。
論文は症例数の多さによって、”そうらしい”と結論付ける精度を高めています。
(厳密には違いますが)多数決みたいなものですよね。

わかりやすく【論文】で説明していきましょう。
精度の高い論文はnの数が多いという特徴があります。
個人の1つの意見では精度が高いとは言えませんもんね。
つまり、調べたケースの数によって、統計的に"そうらしい"と結論付けられています。
すなわち、量が精度を高め、質を決めるのです。
— はせがわ🧭CCS(クリニカルクラークシップ) (@PTsupervisor) March 21, 2020
なぜ『量』と『質』論争がされるのか?その理由とは?
では、なぜこんなにも有名な法則があるのに『量』と『質』論争は未だに続いているのでしょうか?
『量』と『質』論争が続いている理由、、、
それは、実は、ある時期になると『量』よりも『質』を求めたほうが良いといわれているからだと考えられます。
そのある時期とは”成熟期”を迎える時です。
成長のサイクルを
導入期、成長期、成熟期、衰退期
という分類にしたときに、成熟期以降においては『量』よりも『質』を求める傾向にあるとされています。

成長のサイクル「導入期」
この時期は、理学療法士界でいえば、学生さんのことです。
つまり、「質がいい」という概念すらありません。
というのも、ほかと比較のしようがないからです。
学校へいけば、例えその業界の中でもすごい先生が教えていたとしても、その質の高さには気づくことができません。
それがその学生さんにとっては”普通” ”スタンダート”だからです。
成長のサイクル「成長期」
この時期には、理学療法士歴の浅い新人さんが当てはまります。
実際に患者様に触れる機会が増えて、なんとなく理学療法のことが分かり始めたころですね。
量をこなしてきたからこそ、見えてくるものができてくる頃です。
人によっては、ここらへんになってくると、より『質』の高い情報を求め始めるころかもしれません。
成長のサイクル「成熟期」
ある程度理学療法に慣れてきて、その分野に対してある程度の知識を持つことができた人は、一旦成長が止まるような感覚に陥ります。
そんな時、人は貪欲なもので、より質の高い情報を求めていくのです。
同時に、『質』の良し悪しがわかってくるころでもあります。
ここに至るまでに、様々な情報に触れてきたことで比較ができるようになっているのです。

『量』と『質』論争の終わりはない
ここまででわかるように、『量』と『質』論争が続いている理由は、その人の立っているステージによっても異なるからなのです。
初心者のように右も左もわからないときは、”そのとき提供される情報が全て”なので、選択肢を与えられませんから質を考えることすらできません。
しかし、玄人になればなるほど、比較対象が増えてくるため、質の良さを自然と見極め、探し当てることができるようになります。
そうした中で、この『量』と『質』論争が続いているのではないかと考えられます。
つまり、人によっては『量』を重視することも、『質』を重視することもあるのです。
こういった結論のため、結局この論争は、今後も絶えず繰り返されることでしょう。

しかし、ここで覚えておいておきたいのは、成長の段階によって、求めるものが変わってくるという点です。
今、あなたはどんな段階に来ていますか?
そこに合わせた学びをするようにしていきましょう。
実習中、学生として『質』と『量』どちらを重視すべきか?
ここまで『量』と『質』についてまとめてきたわけですが、実習生においてはどちらが重要視されるかわかったでしょうか?
そうですね。
実習生にとって重要なのは『量』です。
実習生は未だ患者様に触れる機会が少なく、机上の空論で物事を話すほか手段がありません。
上述した成長のサイクルでいう「導入期」の段階にいます。
つまり、実習ではいかに多くの患者様に触れ、考え、知恵の引き出しを増やすことができるのか、を重視することをおすすめします。
CCSで重視されるのは『量』
そして、そんな学生さんに朗報です。
これから導入される実習体系であるCCS(クリニカルクラークシップ)は、この『量』を重視しているものとなっています。
従来のように実習中に1〜2人の患者様を深く考察していくスタイルではなく、指導者(臨床教育者)の担当患者様の全員を考察していくスタイルなのです。
そして、その『質』は担保されています。
というのも、指導者(臨床教育者)は全国共通の講習会を受けて、認定を受けたもののみが学生さんを担当することになりました。
つまり、教育に興味があり、教育できるだけの知性を持った人のみが指導者(臨床教育者)となっているのです。
※例外もいるとは思いますが…全員がそうであることを祈りましょう。
なので、学生さんは『質』の良い教育を受けられる環境にあるため、『量』をこなしていくことに注力していきましょう。
これまでの実習では人によって「質の低い教育を大量にさせられる」もの。
これからの実習(CCS)では「質の高い教育を個人の成長過程に合わせて提供する」ものとなった。
学生さんが『量』をこなす際の注意点
ただし、『量』を求める際に注意しておきたいことがあります。
『スピード感』
『改善しようとする努力』
『睡眠時間』
の3つです。
以下に詳しく触れていきます。
『量』を求める際に注意したい『スピード感』
『量』をこなすには、『スピード感』が欠かせません。
『スピード感』をもって取り組むことで必然的に『量』も増やすことができますよね。
CCSではレポートという膨大な時間がかかる課題をしないという選択をすることで、実習中に感じた疑問を解決する時間や患者様と触れる時間に当てることができます。
そうして実習を過ごすことで、どんどん疑問が解消されては、また新たな疑問が生まれ、またそれを解消したと思ったら、また新たな疑問が生まれ…
と言った風に、学ぶ量が増えていくことが見込まれているのです。
それに、『スピード感』を持って取り組むことで、軌道修正もしやすくなります。
実習生にとって臨床で使われている言葉を理解するのは、なかなか難しいこともあるでしょう。
そんなときに怖いのが間違った解釈で学んでいくことです。
それを防ぐためにも、スピード感は欠かせません。
より正確な解釈で理解するためには、"その場"で学ぶことが望ましいですよね。
つまり、『量』をこなすためには『スピード感』を意識しておくことで、より正確でより多くの『量』をこなすことができるのです。
『量』を求める際に注意したい『改善しようとする努力』
と、ここまで『量』をやりましょう!と言ってきましたが、やたらに『量』をこなすのは、タブー。
せっかく『量』をこなすなら、自分なりに改善できる点を一つでも見つけて、次に生かしましょう。
例えば、
患者様がどんな会話なら反応が良いか?
指導者(臨床教育者)への質問のベストタイミングはいつなのか?
与えられた時間内に診療補助を終わらせることができるようにするには、どんなバランスで傾聴とトレーニングをしたら良いのか?
など、昨日より今日。今日より明日。となれるように、改善策を自分の中に持つようにしましょう。
大それたことをしなくてかまいません。
たった1%でいいのです。
その積み重ねが、臨床へ出た時にとても大きな財産となっていますよ。
とはいえ、ただただ時間をかけるというのはお門違いです。
『常に向上しよう』
という意識が必要です。
慣れた作業にならないようにしましょう。
普通の努力ではなく、常に向上することを意識して努力することが重要です。
その"情熱"があなたをエキスパートにするでしょう。
— はせがわ🧭CCS(クリニカルクラークシップ) (@PTsupervisor) March 22, 2020
『量』を求める際に注意したい『睡眠時間』
もうこれは言わずもがなですね!
睡眠時間を削ってまで、ひたすらに『量』をこなさないようにしましょう。
頑張りすぎて身体を壊してしまったら、元も子もありません。
そして、その回復にかける時間がもったいない。。。
なので、
「まだやり足りない‼️」
そのくらいで一旦区切りをつけて、次の日の朝からエンジン全開にすれば良いのです。
案外その方が寝起きも良く、起きてから行動開始するまでの時間のロスも少なくなりますよ。
寝る時間は本当に重要ですからね。
ショートスリーパー?
世界に数%しかいません。
若いから大丈夫?
舐めちゃいけませんよ〜。
それに実習中にうとうとしているのって、患者様だけでなく、他のスタッフにも100%見られていますからね。
あなたを担当する指導者(臨床教育者)に迷惑をかけないようにしましょう。
それもあなたができる実習での成功の秘訣です。
『量』を求める時は、睡眠にあてる時間を惜しまないようにしましょう。
その睡眠があるからこそ、『量』をこなせるのです。
CCSで『量』をこなすためにも『準備』をしよう
そして最後に、『準備』のすすめです。
どんな場面でもそうなんですが、『本番』を成功させたければ、『準備』をしっかりしておきましょう。
『準備』をいかに丁寧に行うかで『本番』は大きく変わります。
プロの選手たちも試合で活躍するために、めちゃくちゃ厳しいトレーニングをしていますよね。
実習も同じです。
実習を成功させたければ、事前に学習しておく必要があります。
リハビリテーションを。
理学療法を。
実習のことを。
この準備のあるなしで、実習は大きく変わります。
せめて、解剖学、生理学、運動学、評価学はチラッとでもいいので復習しておきましょう。
また、こちらも良ければご参照ください。
学生さんにとって未体験である、実習を知ることができれば、なにかと対策のしようがあるかと思います。
【実習前】や【実習中】の準備に必要なポイントを知りたければ、いかの記事を参考にしてくださいね。
特にCCSが始まれば、学生自身が持つ基礎基盤の大きさで進行度合いが大きく変わることになります。
つまり、学生さん自身の『準備』がどれだけできているかで、実習の良し悪しが変わるのです。
実習は何のために行くのですか?
実習は何をしに行くのですか?
何かしらの目標を持って、実習に取り組めるよう『準備』を怠らないようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
引き続き『リハぶっく』をお楽しみください。