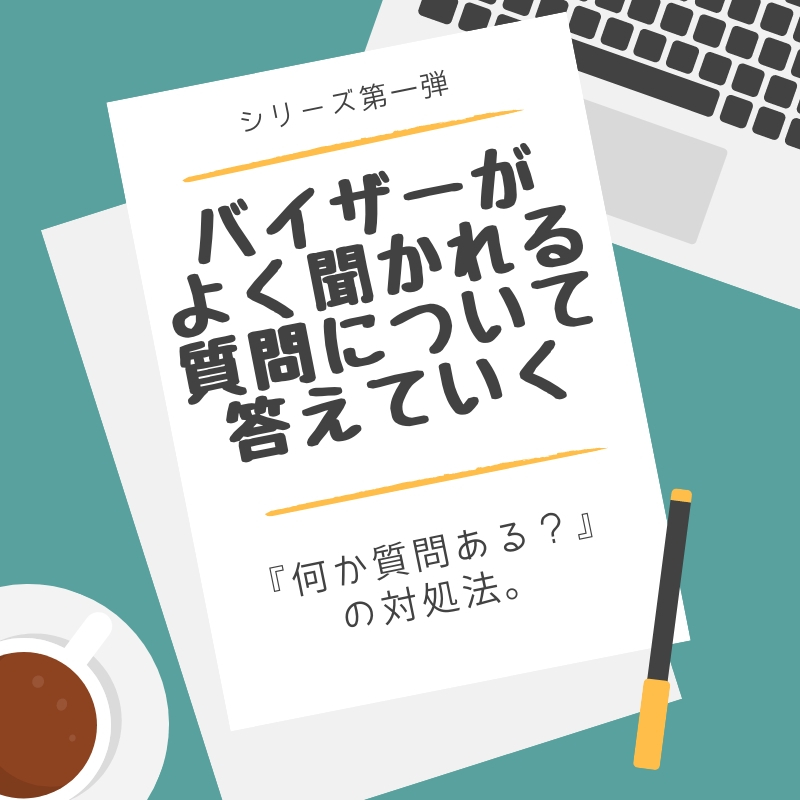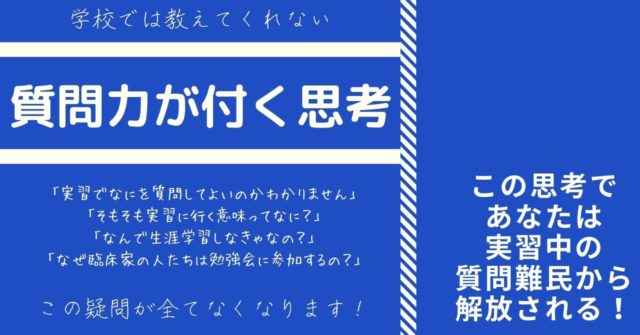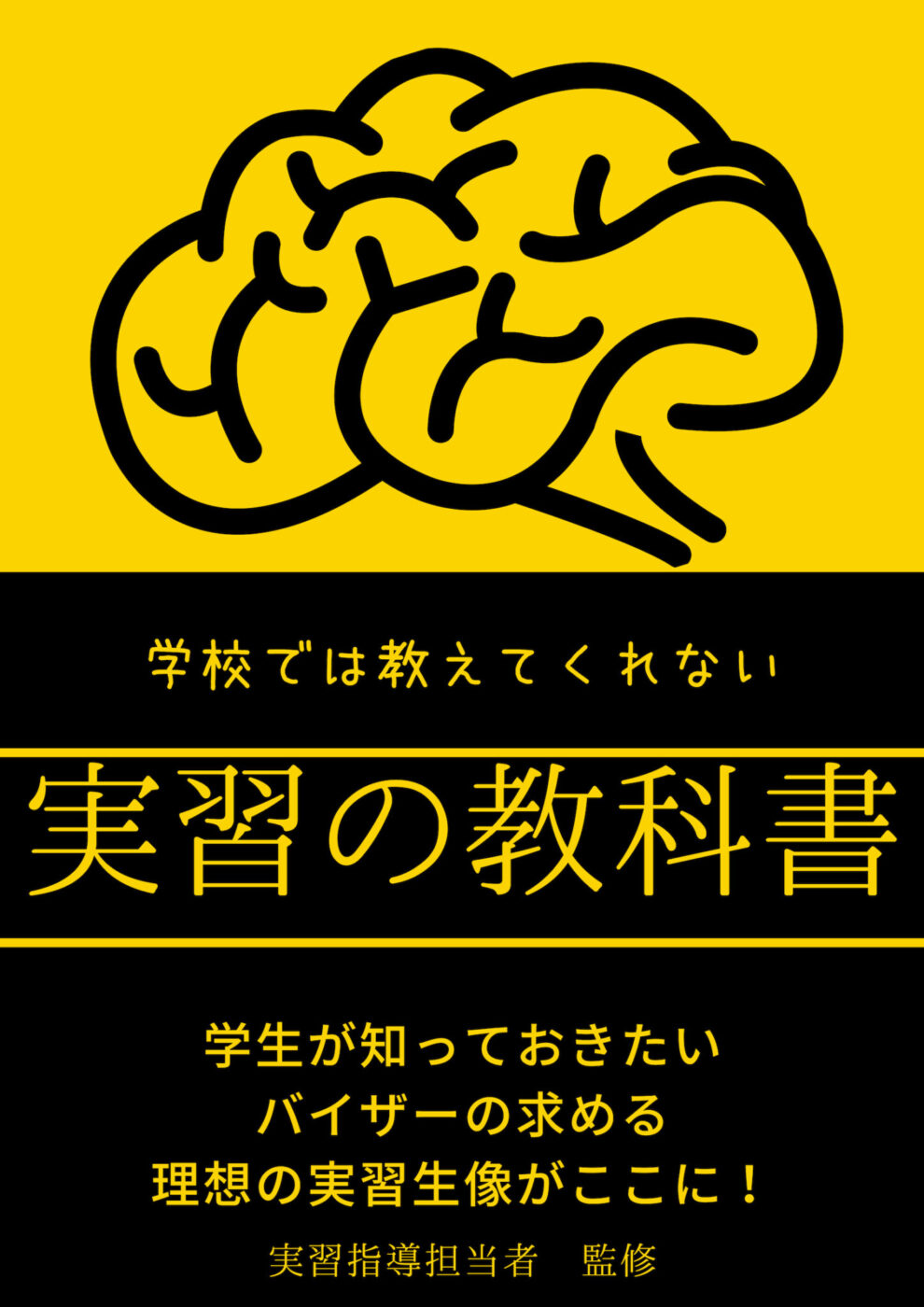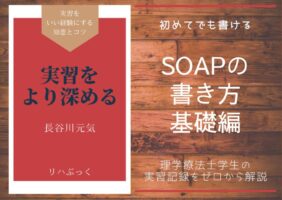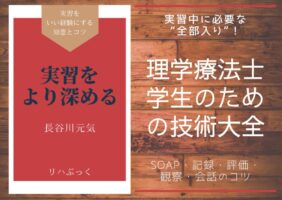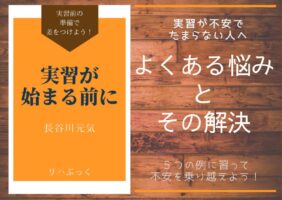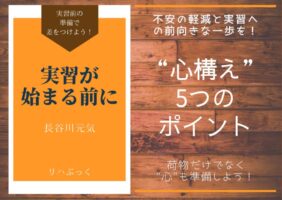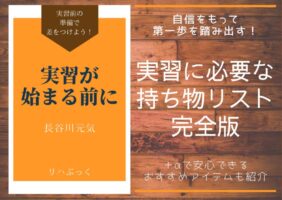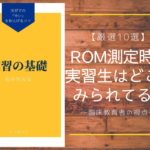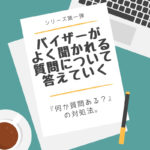どうも、長谷川です。
私はTwitterにて実習生さんの相談を受けているのですが、その時によく聞かれる質問について答えていきたいと思います。
「見学のあと、『何か質問ある?』と聞かれるのですが、質問が思い当たりません。質問したほうがいいのは分かっているのですが、どうしたら思いつくようになりますか?」
今回はこの質問について答えていくことにしましょう。
Twitterにて行ったアンケートでも、過去にそんな仕打ちを受けて困ったことがある方は、76人中89.5%もいたという驚きの結果が出ています。
それだけ多くの指導者が安易に使い、実習生を困らせているのです。
【アンケート】
実習の見学中、
指導者から「何か質問ある?」と言われて困ったことが…#拡散RT希望
— 『リハぶっく』🧭PT実習のコミュニケーション学 (@PTsupervisor) March 10, 2021
※アンケートにご協力くださった方々、ありがとうございました!!
そんな実習あるあるに対して今回はメスを入れていきます。
目次
CEが放つ「何か質問ある?」の意図とは
まず、この問いをよくする指導者の意図としては
①実習生の実力が知りたい。
②次のリハビリまでの時間が詰まっていて、早く切り上げたい。
③何を教えてよいか、わからない。
という大きく分けて3点が挙げられます。
実習生さんはこれのうちどの意図でCEが問いを立ててきたのかを判断して、返答を行う必要があります。
これらの見分け方はそんなに難しいものではないので、以下のような対策を練って返答していきましょう。
では、ひとつひとつ詳しく触れていきます。
CEの意図①実習生の実力が知りたい。
多くの場合がこのパターンです。
このパターンのCEは、実習生さんからの質問内容によって、”実習生さんがどのような視点で見学をしていたのか”を把握できると考えています。
指導する側には治療の明確な目的があり、それを治療しているときに見学してもらいたいのです。
そのときに、指導者が見てもらいたいポイントと実習生さんの質問内容が合致しているときに、『おっ。ちゃんと見学をしてくれたんだな』と嬉しく思うものです。
治療中、セラピストは患者様に対して、”○○を改善するための治療をやってるんですよ!”と意識付けをしながらメニューを組んでいます。
というのも、意識付けをすることで治療効果を増幅させることができることが知られているからです。
そのため、誰もが理解できるように、わかりやすく、かつ治療箇所を絞って治療を行なっています。
つまり、この場合の「何かある?」の質問を言い換えると、「明らかな治療目的に気付けた?」とも言い換えられます。
なのでこの場合、”実習生のあなたからみて、治療目的がどういう風に見えたか”を答えてみましょう。
その着目点の正誤に関しては、気にしなくてかまいません。
良いCEであれば、合っていたからといって、さらに難しい質問がきたり、間違ったからといって、怒ったりはしません。
もちろん、わからなかったら、わからなかった旨を伝えれば大丈夫です。
※見学の事前に着眼点を聞き出してから、入るとこの質問に対して過剰に怖がることもなくなるかもですね!
このタイプの問いは着眼点について加筆・修正をするための問いだと考えましょう。
学生のうちですから、自信がなくてあたりまえですし、間違って当たり前です。
むしろ、自己解決してしまい、その先生の考え方が聞けないのはとーーーーっっっても、もったいないです。
その患者様にしている、個別の工夫もそこから聞き出せるかもしれませんので、自分がどう見えたかを素直に伝えてみましょう。
見学していて目的がわからなければ、「どんなことを目標に治療をしていたのかわからない」ことをきちんと伝えましょう。
そして、なんのために治療していたのか、どこに着目して見学したらよかったのか、先生から聞きだしましょう。
次回入らせてもらった時に、その視点でみることができます。
「わからない」ことはハズカシイことではないですよ。
学生のあなたにとっては ”当たり前” "当然" のことです。
それは多くのCEもわかっています。
なにせ自分もそうだった過去があるでしょうからね。
見学は、一人のセラピストの考え方を聞く絶好の機会です。
臨床に出れば、一人のセラピストの考え方を聞くために、高いお金をだして講演会に出席したり、勉強会に参加したり、参考書を読んだり、文献を精査しなければなりません。
それを実習を通じて大変価値のある話を毎日、何症例も聞くことができるのですから、こんなにいいことはありません。
私も今できることなら、他病院の見学に入らせてもらいたいと想うくらいです。
見学で学んだ考えを自分の将来の知識となるように理解し解釈していくことが、見学時の大切な目的の一つであることは間違いありません。
変にプライドが高くて、「どうせ、あの治療をしているんでしょ」なんて、自分なりのみで解釈していると、臨床にでてから痛い目をみます(私がそうでした 笑)。
ちゃんとした自信をつけるために、プライドなんて捨てて、先生の考えを聞きだすことに専念しましょう。
そうすれば、その浅い考えで思考がとまることもなくなり、よりリハビリテーションが面白く感じるはずです。
CEの意図②「次のリハビリまでの時間が詰まっていて、早く切り上げたい」
これは、学生さんには申し訳ありません。
セラピスト側の技量や忙しさの問題です。
言い訳ではないのですが、、、
我々セラピストは1単位20分を目安にリハビリを提供しています。
看護師さんのように、存在していることで報酬が得られる職業ではないのです。
セラピストはこの時間をきっちり患者様に提供することで報酬を得ているため、一日のタイムスケジュールが分単位で組まれています。
つまり、この場合の「何かある?」の質問を言い換えると、「急いでいるから、質問は後で受けるでもいいかな?」とも言い換えられます。
なのでこの場合、”質問項目が何点あるかを提示した上で、いつなら質問する時間的余裕があるか”を聞いてみましょう。
「質問したいことが○点あるのですが、お時間よろしいですか?」なんて感じで大丈夫です。
こうして事前に聞いてもらえば、快く時間を作ってくれるはずです。
また、次に見学に入らせてもらったときもそのような対応をするセラピストであった場合、治療中に質問しても良いか事前に聞いてみましょう。
そうすることで、思い出しながら解説する手間も、時間を割く手間もなくなるので、喜ぶセラピストは多かったです。
もちろんその際は、患者様との会話の邪魔にはならないよう、適度な質問量で、そして、ご本人の前で話せる内容のものを取捨選択する配慮が必要になりますのでご注意ください。
③何を教えてよいか、わからない。
このケースも少なくない印象です。
これは指導する側と実習生側とのコミュニケーション不足が主な原因で起こるものです。
実習生さんが何を見学時に学びたいのか、実習を通してなにを学びたいのか、模索しているときに良く聞かれる問いです。
つまり、この場合の「何かある?」の質問を言い換えると、「実習・見学の目的はなにかな?」とも言い換えられます。
なのでこの場合、”①のようなあなたが感じた今回の治療目的を質問したあとに、自身の見学の目的(実習の目的)を伝えて、それに合致する患者様がいないかどうか”までを聞いてみましょう。
このように少しでもコミュニケーション量を増やすことで、お互いに誤解なく関わることができると思います。
セラピストには、実習生の反応次第で話す内容を決めているタイプもいます。
実習生の反応に対して、それに呼応するような形、つまり「聞きたいことがあったら聞いて」というスタンスをとるセラピストがいるのです。
実習生さんにとっては”冷たい”や”怖い”と感じることも多々あるとは思いますが、教えることにまだ慣れていなかったり、自信がなかったり、プライドが高い場合など、セラピスト自身に問題があることもありますので過剰に捉えないようにしましょう。
こういうCEはコミュニケーションを重ねることで、一旦あるボーダーを越えてしまえば親身になって、とても多くを教えてくれるタイプでもあります。
なので、ボーダーさえ越えてしまえば、他のセラピストよりも有益な情報が得られることが多いため、見学に入らせてもらう頻度を多くしてみることも1つの戦略でしょう。
私は長期実習のときに、「期間内にその方の牙城を崩す」というサブテーマを挙げて接した先生がいました。
何度も見学にはいらせてもらい、実習の後半でやっと牙城を崩した結果、唯一臨床に出てからもずっと関わりを持たせていただける先生となるという不思議な関係性を持つことができました。
そこまでにはならないにせよ、このタイプの先生は信頼関係を結ぶことができてしまえば、他の先生方よりも良好な関係になりやすいという一面もありますので、ご参考までに。
また、「もっと質問力を上げたい!」という方は、こちらもご覧下さい!
こちらには、
・実習にいきたくなる
・実習で質問をしたくなる
・学校の授業を真剣に受けたくなる
・勉強の楽しさを感じることができる
ために必要な知識を詰め込みました。
この知識のあるなしで、実習だけでなく、臨床にも差が出てくることです。
臨床でスタートダッシュを決めたい方は、一読をおすすめします!
☟これを読めば実習中の質問に困ることはなくなるでしょう☟
まとめ
以上が「何か質問ある?」という言葉の指導者側の意図です。
実習生にとっては凄く困ってしまうこの問い。
指導者がどんなことを思って発した言葉なのか、少しでも参考になれば幸いです。
指導者にとっては何気なく使っている言葉ですので、中には実習生を困らせているという自覚のない指導者もいます。
すでに良い関係を構築できているのであれば、それとなくその問いが困ることを伝えてみるのも一つの手です。
「何かある?」
「大丈夫です。」
そんなつまらないやり取りはもうおしまいにしましょう。
それがあなたのためになるのだから。
もし、なにか記事にしてほしいことがあれば、ご連絡頂けると幸いです。
お待ちしております。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。