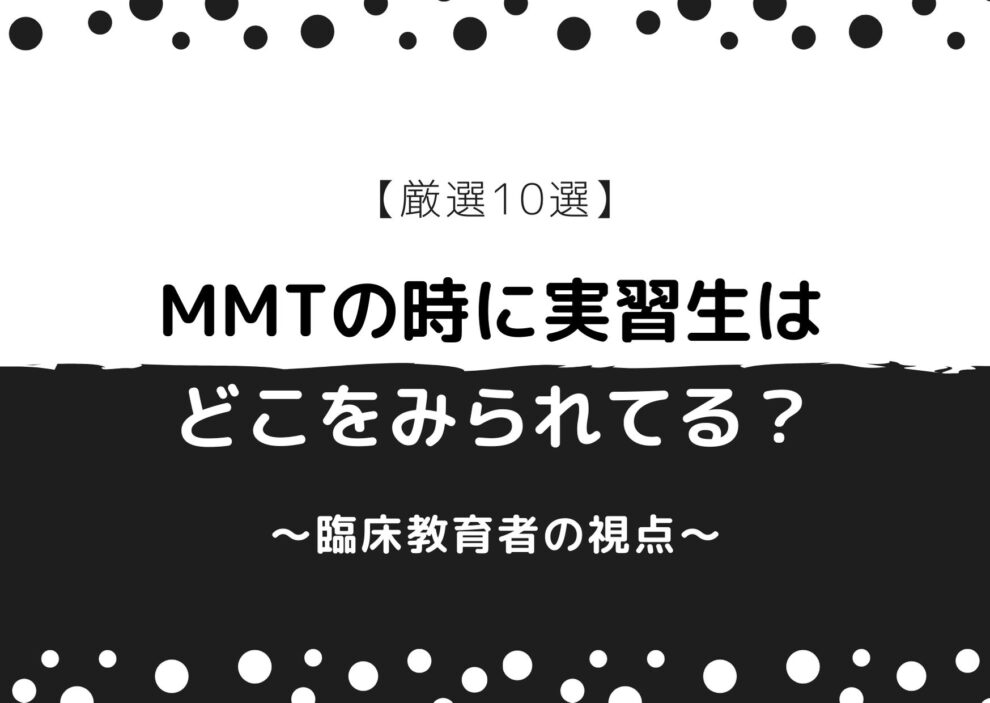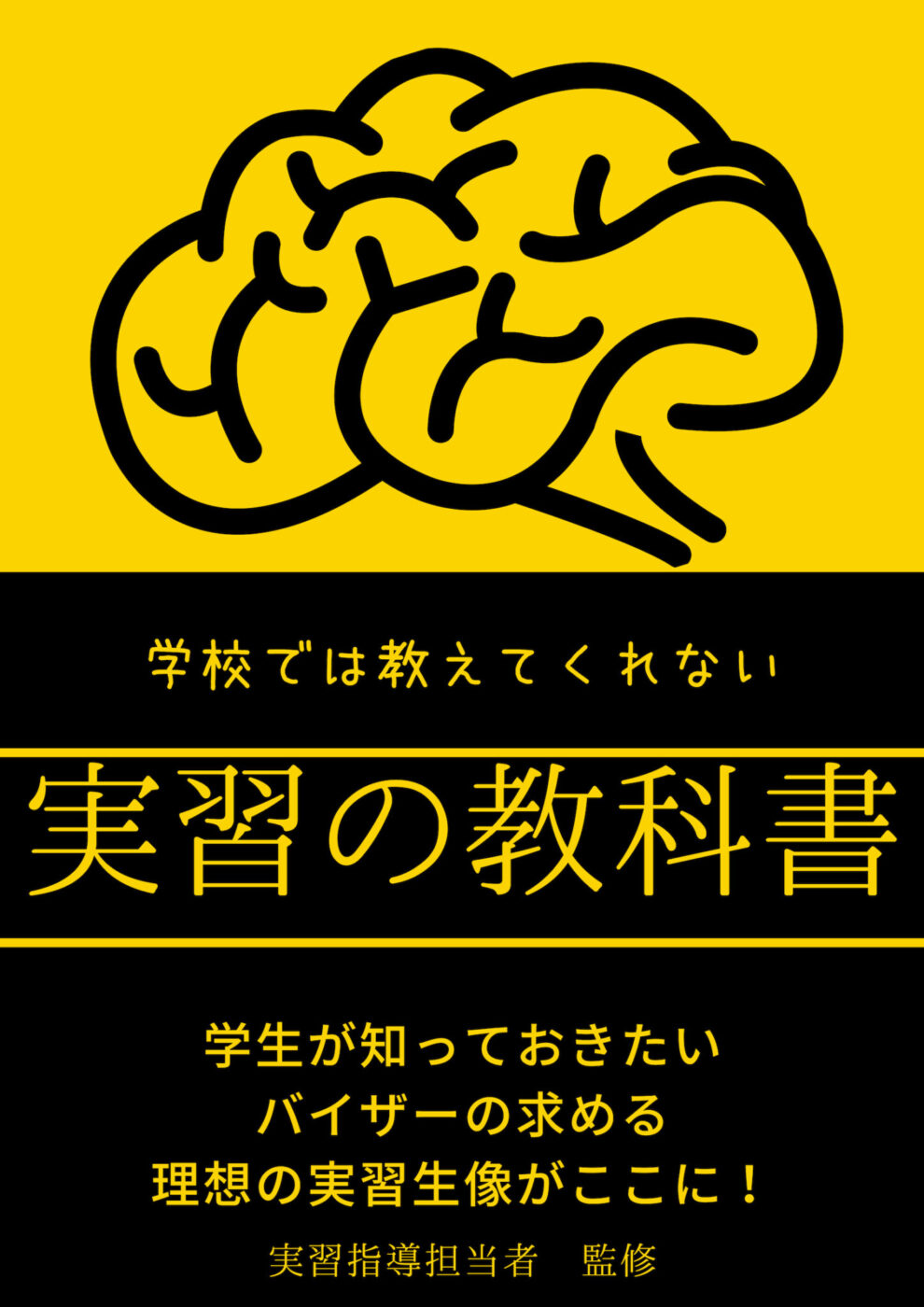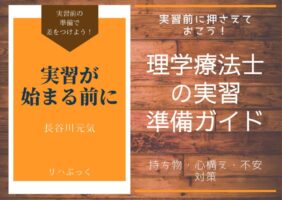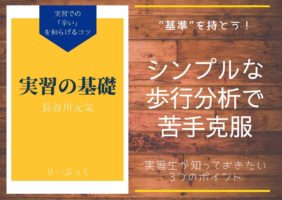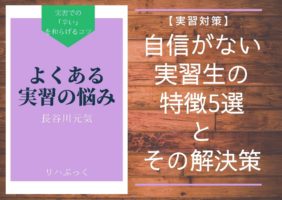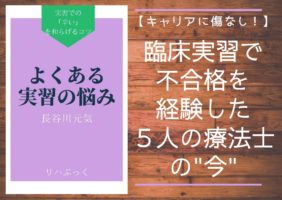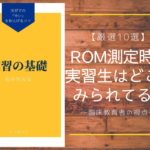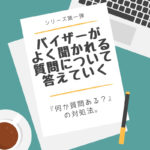MMTは理学療法士の基本的な検査測定技術
実習中、必ず経験するであろうMMT。
学生さんにとっては、初めて患者様に触れる機会でもあり、とっっっても緊張する検査の一つですよね。
友達や親族などのいわゆる”健常者”を相手に練習していたときとは異なり、実際に痛みや代償動作のある患者様を相手に測定したあの感触と緊張感は、実習を終えて何年も経った今でも鮮明に覚えています。
さらに、学生さんにとっての大きなの悩みは、臨床教育者(指導者)からはその姿をチェックされ、反省点のフィードバックを受ける。。。という点です。
このように、なかなか過酷な環境でMMTをすることを強いられる実習では、いくら練習を積んできたとしても、本来の力で円滑に行えないのも当然ですよね。
ただ、
患者様への配慮も!
臨床教育者へのアピールも!
なんて考えていたら、身体がうまく動かなくなってしまうのが目に浮かびます。
そこで、今回はMMTをする際に臨床教育者が実習生さんのMMTの時に、どういったところをチェックしているのかの例をまとめました。
これらを頭に入れながら、MMTの練習をしていくことで、MMTの技術も向上するので、ぜひお試し下さい。
目次
MMTの基礎
では、まずMMTの基礎から復習していきます。
MMTとは
MMT(徒手筋力測定)とは、各筋肉あるいは筋群の筋力を徒手で主観的に測定することを指します。
日本ではDaniels法が広く普及しており、「0~5」の6段階のグレードで筋力低下の程度を測ることができます。

MMTの分類と基準
以下、MMTのグレードの分類と基準の表です。
| 5 | Nomal | 強い抵抗を加えても運動域全体にわたって動かすことができる |
| 4 | Good | 抵抗を加えても運動域全体にわたって動かすことができる |
| 3 | Fair | 抵抗を加えなければ、重力に抗して運動域全体にわたって動かすことができる |
| 2 | Poor | 重力を除去すれば運動域全体にわたって動かすことができる |
| 1 | Trace | 筋収縮がわずかに確認されるだけで、関節運動は起こらない |
| 0 | Zero | 筋収縮は全く見られない |
MMTの記載方法
「MMTの書き方がわからない!」という学生さんも多いようですね。
MMTは”関節運動”を検査対象にしているため、「肘関節屈曲MMT5」などと【関節運動+グレード】で表記します。

MMTの目的
・筋力低下の程度の判定
・診断の補助
・治療目標の設定
・治療効果の判定
MMTからわかること
上記の目的を学生さんにもわかりやすく噛み砕くと、MMTをすることで以下のようなことがわかります。
・関節を動かすことのできる範囲
・神経障害の部位
・筋力の程度
・生活への影響
・認知機能の程度
・改善可能かどうか
・改善したかどうか
など
これらのわかることを参考にしながら、セラピストは理学療法を提供しています。
なので、この評価が曖昧であればあるほど、セラピストの提供する理学療法はテキトーなものになってしまいます。
つまり、結果として、患者様の回復への道を遠回りすることに繋がるのです。
そのため、セラピストは正確に、かつ、再現性を持って行う技術を求められます(MMTに限らない)。

MMTの注意点
グレード5が「Normal(普通)」です。
時折、アスリートがグレード5だと思っている方も少なくありません。
評価基準をしっかりと把握しておきましょう。
また、患者様の多くは筋肉低下がみられています。
その中で最大抵抗をいきなりかけてしまうと筋の損傷に繋がることもあります。
基本のやり方として、MMTはブレイクテストで行いますが、その際の抵抗力は徐々に上げていく等の配慮をしましょう。
実習生さんがMMTをする際に臨床教育者からチェックされるポイントとは?
さて、MMTの基礎を復習したところで、ここから実習生さんがMMTをする際に臨床教育者からチェックされるポイントを10コ紹介していきます。
MMTでチェックされるポイント①「目的は明確か?」

なぜ、その箇所の筋力を評価しなければならないのかという目的を明確にしておきましょう。
たとえば、THAの術後の方に対して股関節のMMTを評価する目的は”手術の影響を把握するため”などのように明らかですよね。
しかし、その方に対して、足関節や膝関節、体幹のMMTを評価する目的はなんでしょうか?
別に評価しなくても良いのでは??
…そういうわけにもいきませんよね。
多くの場合、手術した関節の周囲にも何らかの影響が及んでいることもあります。
また、手術の経過次第では、その周囲の組織で代償していくことも考える必要があります。
そういったこともあり、臨床では症状の出ているところ以外のMMTにも着目して評価を行うことがあります。
このことに関して評価される側として患者様は疑問に思うこともあるでしょう。
その時に、なぜここのMMTを評価しているのかという目的を答えることができなければ、それは”無駄な評価” ”無駄な時間”であると判断されてしまいます。
しっかりと目的意識をもってMMTに臨みましょう。

MMTでチェックされるポイント②「インフォームドコンセント」

患者さまへの説明は必ず行いましょう。
インフォームドコンセントは医療人として”当たり前”となっているものです。
臨床に行っても必ず行うものですし、自分の身を守るためも必要になってきますので、これを重視する臨床教育者も多いです。
これからどんなことをするのか、それをすることでどんなメリット・デメリットがあるのかを提示しましょう。
その上で、測定をしてよいかの同意を得てください。
”見知らぬ人、増して学生という立場の人にいきなり何かをされる”という恐怖は計り知れません。
その不安を少しでも解消していただくためにも、インフォームドコンセントは重要な役割を果たします。
また、インフォームドコンセントを行う際は、医療に携わらない一般の方にも伝わるよう、難しい言葉はわかりやすく言い換えましょうね。

例えば、「これから押しますが、このまま(膝を伸ばしたまま)耐えててくださいね!」といわれる方が理解しやすいですよ!
実習としては、そうした一言一句を臨床教育者が聞き、説明方法の改善案を提示してくれるでしょう。
インフォームドコンセントのようなものは他人から指摘されることで、改善していくものです。
積極的に言葉遣いや言葉のチョイスセンスなどのフィードバックを受けにいきましょう。
MMTでチェックされるポイント③「代償動作を見逃していないか?」

筋力は代償動作の有無によって大きく値を変えてしまいます。
例えば、股関節屈曲のMMTは体幹の前傾or後傾、手を付いて踏ん張るなどの代償動作がみられることがあります。
テストとしては代償動作のない筋力を測定することが目的のため、体全身をみておくようにしましょう。
ただ、ここで注意したいのが「これらの代償動作は決して”悪”ではない」ということです。
MMTの評価として純粋な関節運動の筋力を測る上では、嫌がられがちです。
しかし、代償動作は「弱い部分を補うことができる」「うまく体を使えている」という評価の一面もあります。
純粋な関節運動ができる人はそう多くありません。
まして体の弱った患者様ならなおさらのこと。
どう補って生活しているのか、そして、それが悪影響をもたらす因子となっていないか、を他の評価と統合したときに吟味していきましょう。
MMTでチェックされるポイント④「抵抗をかける位置は適切か?」

抵抗のかける場所は、MMTの正確さを高めるために気をつけたいポイントです。
”てこの力”で有名な「力のモーメント」のこと覚えていますか?
支点・力点・作用点の位置関係で力の大きさが変わってくるというアレです。
この法則では支点から作用点が離れれば離れるほど、力点の力が大きくなるという性質があります。
MMTでそれらを置き換えると、
支点 ⇒ 関節の回転軸
力点 ⇒ 筋肉
作用点 ⇒ 抵抗
となります。
つまり、関節の回転軸から抵抗が離れれば離れるほど、筋肉が収縮しなければならない力が強くなるということです。
臨床場面に落とし込むと、「検査者の抵抗のかける位置が違えば、被検査者の発揮する筋力が変わってしまう」ということもありうるのです。これらから、再現性を高めるためには複数回行う(再評価する)際は、同じ位置で抵抗をかける必要があるのです。

MMTでチェックされるポイント⑤「評価にかける時間を気にしているか?」

セラピストにとって評価することはとっても大事なことです。
治療の方針を決めるためには必要不可欠なものですからね。
ただ、患者様としては評価をすることよりも、早く安楽になりたいと願う方もいらっしゃいます。
また、一度に介入できる時間も20分間であることも多く、評価にかける時間と治療にかける時間の配分が難しいのです。
今日は評価だけで終わりました、、、となってしまうと、患者様との関係性にも影響が出てきそうですよね。
なので、なるべく早く・正確な評価をする技術が求められます。
実習だから、、、
なんて言い訳は通用しません。
患者様にとっても貴重なリハビリの時間。
その配慮ができている必要がありますよ。
MMTでチェックされるポイント⑥「測定結果を報告しているか?」
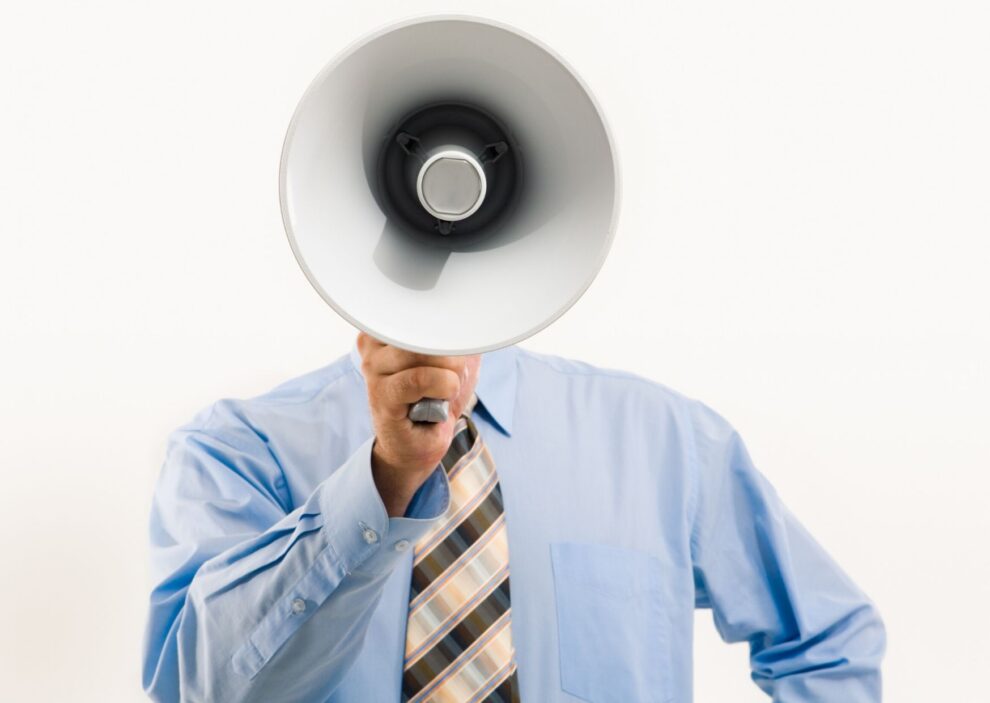
測定結果(考察は含めない)を患者様に伝えましょう。
よく測定結果を伝えていない学生さんがいますが、それは良くありません。
だれしも検査したら結果が気になりますよね?
そのアナウンスがあるかないかで次第であなたと患者様との関係性が変わっていきますからね。
また、臨床教育者にとっても、学生さんが測定した結果が気になります。
その値が妥当かどうかの判断をその場ですることもできるので、測定結果の報告はその場で、するように心がけましょう。
MMTでチェックされるポイント⑦「バイタルに変動がないか確認しているか?」
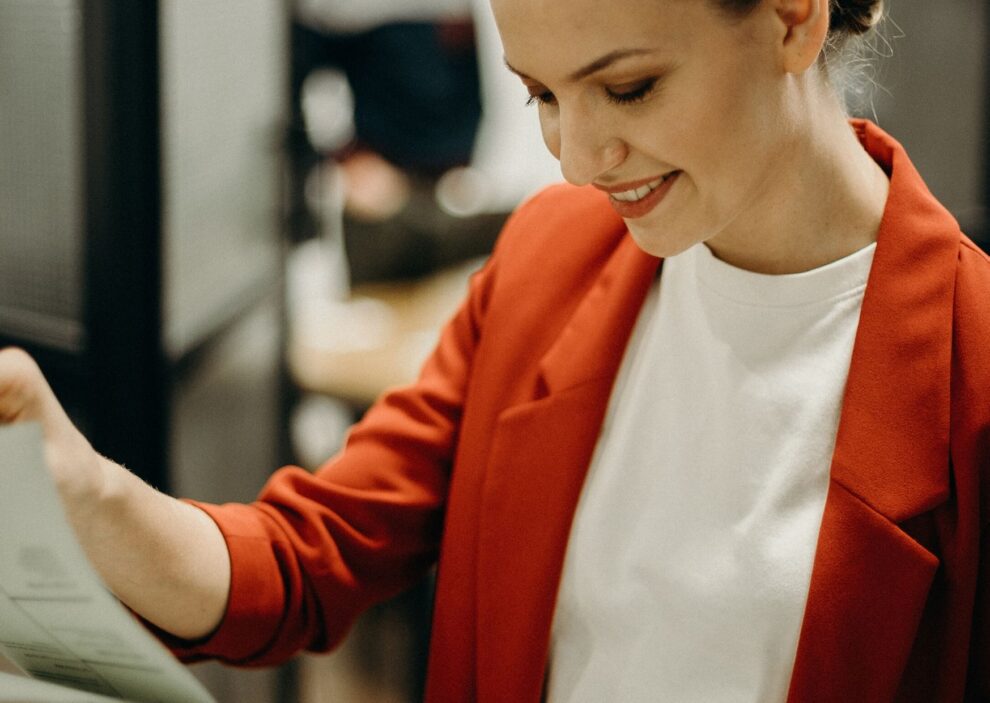
評価をすることは、時に身体への負担となります。
なので、MMTでは最大筋力を発揮してもらうことになりますので、バイタルの変動を認めることがあります。
特に評価時に”息こらえ”をしていて、血圧上昇、失神(迷走神経が刺激されたことによるもの)などの症状が出る可能性がないとは言い切れません。
しかし、学生さんは評価箇所に集中してしまい、全体を見ていなくて、気付くことが遅れてしまうこともしばしばみられます。
評価中はなるべく視野を広げて、抵抗をかける場所を決めるときのみ評価箇所に目を向ける…などの工夫をしていきましょう。
患者様の中には、バイタルが変動していても、気を遣って言葉に出さない方もいらっしゃいます。
些細な変化に気付いていくことで関係性も良い方に向きますから、MMTの時は全体をみてバイタルサインの変動を確認しておきましょう。
MMTでチェックされるポイント⑧「見た目を気にかけているか?」

評価をする際、どうしても患者様の衣服が乱れてしまうことがあります。
また、患者様の着る病衣が浴衣スタイルであることもあります。
すると、はだけることもありますので、注意が必要ですね。
特にMMTでは筋腹をみる機会があるので、その際は十分にプライバシーを考慮しておきましょう。
そして、評価している側の見た目、つまりあなた自身の見た目も気にかけてください。
変な姿勢で評価していないか?
不安定な姿勢になっていないか?
礼儀のある姿勢になっているか?
患者様との距離感はどうか?
臨床の場では、他の患者様もいます。
セラピストは常に見られる立場でもありますから、自身の見た目にも配慮していきましょう。
MMTでチェックされるポイント⑨「体力を考慮しているか?」

MMTは筋力を測定するものですので、とても疲れます。
患者様の多くは体力が低下しているので、一度に複数箇所の評価をすることはとても疲れます。
そして、疲れている中で評価しても、再現性の高い正確な評価とは言えなくなるなります。
なので、患者様の体力に合わせて、適切な量の評価数、適切な休憩時間も考慮しておくようにしましょう。

MMTでチェックされるポイント⑩「基本肢位が取れない場合の別法を用意しているか?」

MMTには背臥位の他に、側臥位、腹臥位、立位で評価するものがあります。
患者様の中にはそうした姿勢を取ることができない方がいるということを把握しておきましょう。
例えば、
・円背の強く、背臥位になれない
・骨折による禁忌肢位がある
・腰が痛くて腹臥位が取れない
・脚の筋力が弱くて立っていられない
などのことがあります。
その際に、基本肢位以外の別法を知っているかどうかで、評価ができるできないが変わってきます。
また、事前に患者様の取れない肢位を把握しておけば、患者負担の軽減、時間短縮などの効果もみられます。
評価方法はいくら知っておいても損はないので、しっかりと予習しておきましょう。
以上、実習生さんがMMTをする際に臨床教育者からチェックされるポイント10コでした。
これらを注意することで、臨床教育者からのフィードバックの質が上がるだけでなく、MMTの技術も上がります。
ぜひ、一つ一つ意識しながら、練習してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
引き続き【リハぶっく】をお楽しみください。