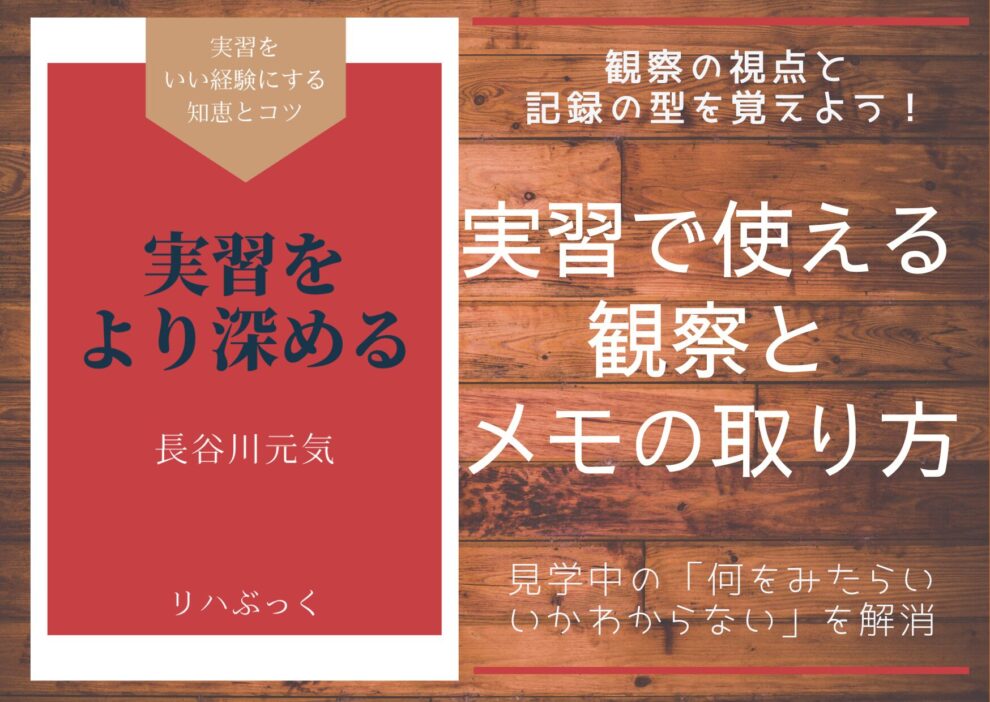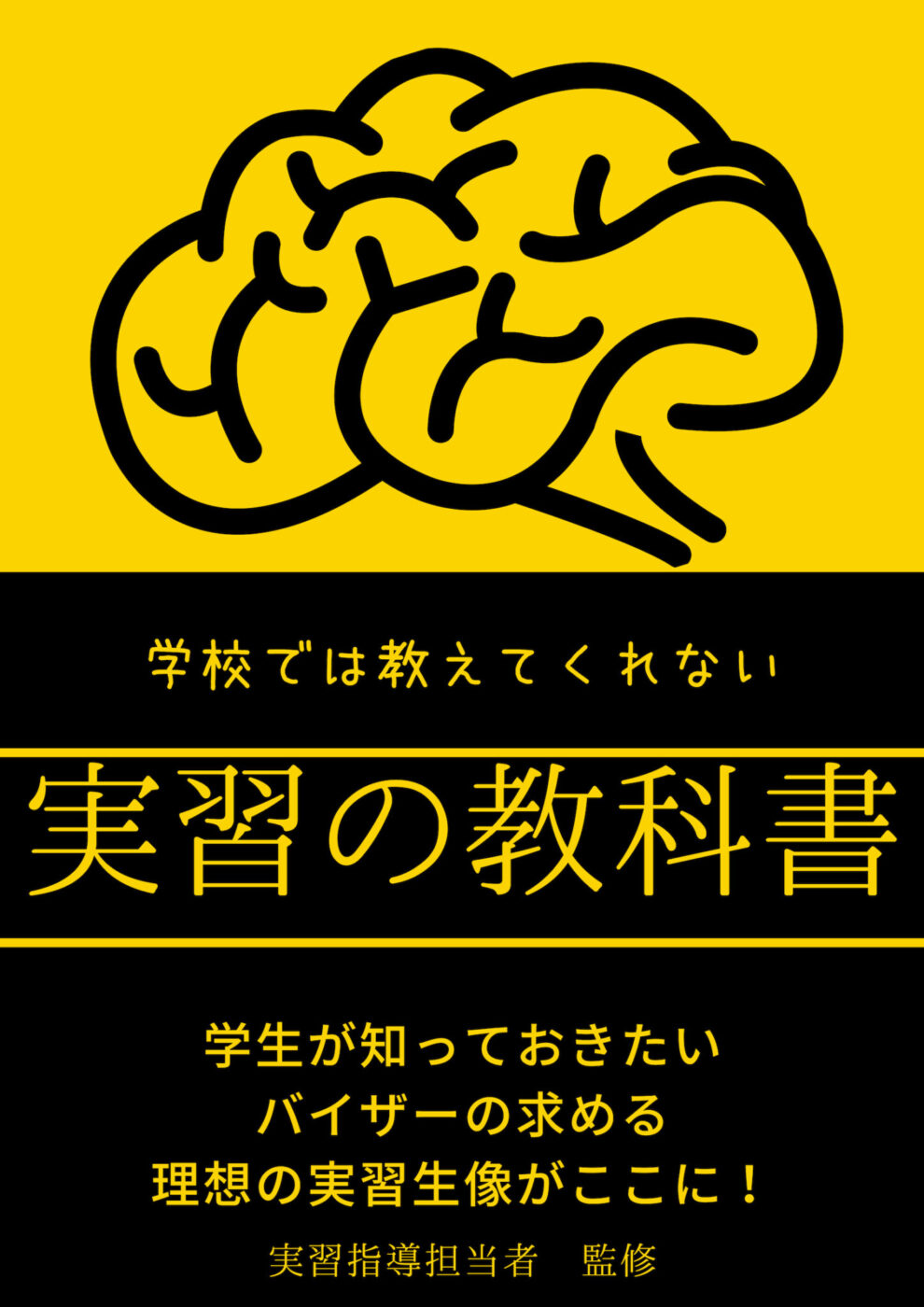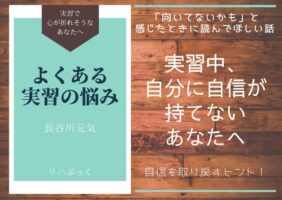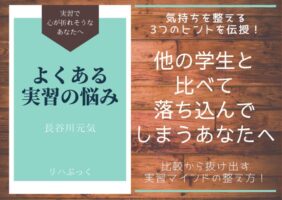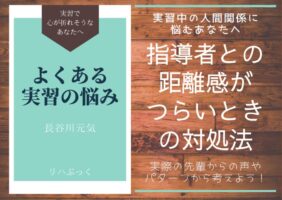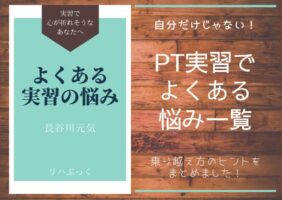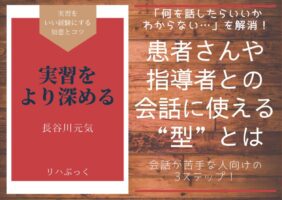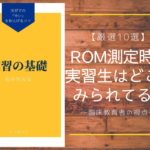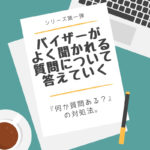「何を観察したらいいのか、まったくわからない」
「見たことをどうメモにすればいいのか悩む」
その不安、すごくわかります。私も最初そうでした。
でも、大丈夫。いきなりすべてを完璧に見る必要はありません。
まずは「観察の視点」を持つこと。そして「記録の型」を覚えること。
この記事では、初心者でも実践しやすいテンプレートを使って、「観察→メモ→SOAP」の一連の流れを紹介します。
/

この記事の目的
臨床実習での観察やメモに苦手意識がある学生へ向けて、「見る視点」と「書くコツ」をテンプレート付きで解説。
代償動作の見抜き方や、観察メモからSOAP記録へ自然につなげる方法も紹介します。
目次
初心者でもできる!観察メモの基本テンプレート
5つの定番観察ポイント〜“観る場所”を絞ろう〜
以下の5点を観察ポイントとして覚えておきましょう。
- 姿勢(臥位・座位・立位)
- 歩行(左右差、テンポ、バランス)
- 移乗(立ち上がりや座り方)
- 表情・しぐさ(痛みや不安のサイン)
- 使っている道具(平行棒や歩行器、装具の使い方)
最初はぼんやりとでも構いません。
学校で習った”正常”と比べて、”異常”だと感じた点をメモしていきましょう。
「なんか普通とは違うんだよな…」と違和感を覚えたところをメモするのがコツです。
観察メモのテンプレを使ってみよう!
次のステップとしては、その違和感を以下の観察メモのテンプレに当てはめていくことで、思考の整理をしていきます。
- 時系列でメモする(動作の流れ)
- 部位と左右をはっきり(例:右膝、左肩)
- 印象ワードを使う(例:ぎこちない、速い、ためらいあり)
- 事実と感想を分ける(事実:立ち上がりに3秒、感想:重そう)
これを実際に当てはめてみると、、
【動作名】立ち上がり
【姿勢・準備】手すりに手を置き、足を引いて構える
【動作】1回目:一気に立ち上がるが、右脚に体重乗っていない
【印象】動作速いが、慎重さなし。右膝に不安?
【補助】なし
【主観メモ】見た目より軽快。本人は「平気」と言うが…
このような感じになったら上出来です(実習の後期ではもっと専門用語が増えているといいですね!)。
ちなみに、このようにうまくまとめられた実習のメモは「理学療法士になった自分」への伝言にもなります。
臨床で壁にぶつかった時に、このメモに記された知識に助けられることもあるでしょう。
なので、このメモを読むと情景が浮かぶように書いておきましょう!

代償動作を見抜くコツと記録の型
代償動作の典型パターンを覚えておこう
学校で習う”普通ではない”動作の代表例である『代償動作』。
その代償動作の良し悪しは一旦置いておいて、実習中に観察しやすいものとして覚えておきましょう。
我々、理学療法士がよく見る「定番の代償動作」は以下のようなものです。
- トレンデレンブルグ歩行:骨盤の左右傾斜に注目
- ぶん回し歩行:股関節や膝関節の可動域制限をカバー
- 膝反張:大腿四頭筋やバランス機能の低下による補償
- 反動をつけた立ち上がり:下肢筋力または体幹の弱化のサイン など
観察のコツとしては、まずは左右差を見ておきましょう。
代償動作は「無理してるサイン」です。
それをメモできると、SOAPのAも書きやすくなります。
代償動作のメモのコツ〜「〇〇しながら□□」で書くと伝わる〜
代償動作をメモする時のちょっとしたコツですが、みた動作を”〇〇しながら□□”のように書き始めてみましょう。
例えば、
- 「右下肢遊脚期にぶん回し運動しながら、歩行している」
- 「常に左手で把持物に体重を預けながら、座位を保っている」
- 「ベッド端座位→立位の動作時、上肢で反動をつけながら立ち上がった」
のように書いておくと、より伝わりやすくなっていますよね。
観察メモからSOAPの記録へ。つなげ方は“順番を意識する”だけ!
「見たこと」がOになる、「気づいたこと」がSになる
これまで、観察する時のポイントや、まとめ方に触れてきました。
では、これらをすることで、何が良いのかというと、、、
前述の観察テンプレートを使うことで、自然とSOAPに分けられるようになります。
というのも、
| 観察メモのパーツ | SOAPでの位置づけ |
|---|---|
| 客観的に見た事実 | O(Objective) |
| 主観的な気づきや印象 | S(Subjective) |
このように振り分けると、上に挙げた観察メモの例では
S(Subjective)
本人より「立ち上がりは平気」との訴えあり。
O(Objective)
立ち上がり動作1回目において、手すり使用し、足を引いた状態から一気に立ち上がる。
右下肢への荷重が不十分であり、動作全体はスピーディーだが慎重さに欠ける印象。補助は行わずに自立で実施。
A(Assessment)
立ち上がりは自立可能だが、右下肢荷重回避が疑われる。主観的には問題を感じていないが、潜在的な右膝不安の可能性がある。動作に速さがある一方で、バランスや制御の面に課題がみられる。
P(Plan)
右下肢荷重への不安に関して評価の必要性あり。必要に応じて段階的な荷重訓練や動作速度の調整を指導予定。
このように変換することができます。
SOAPに慣れていない学生さんも、いきなりSOAPで書こうとせずに、このような順を追って書いていくことで悩む時間を少なくできそうですよね。
関連記事:【学生向け】実習の記録が変わる!デイリーノート×SOAPの活用法。(有料note)

最後に:「気づき→調べる→納得」の繰り返しが“観察眼”を育てる
実習の見学中に「何を見たら良いのかわからない」という方は、ぜひこの記事を参考に観察メモをテンプレ化して、SOAPに落とし込むようにしてみましょう。
そうすれば、
どこを見るべきなのかがわかり、
その気になった動作や姿勢を「なぜ?」と考えるようになり、
その疑問をすぐに指導者に聞いたり、教科書・ネットで確認したりすることができると思います。
こうして、見るべきポイントがわかったあなたは、次の日の観察でより“意識して見る”ことができ、それが習慣となっていくことでしょう。
そうなれば実習中の見学も、今よりもう少し楽しい時間になっていくかもしれませんね!