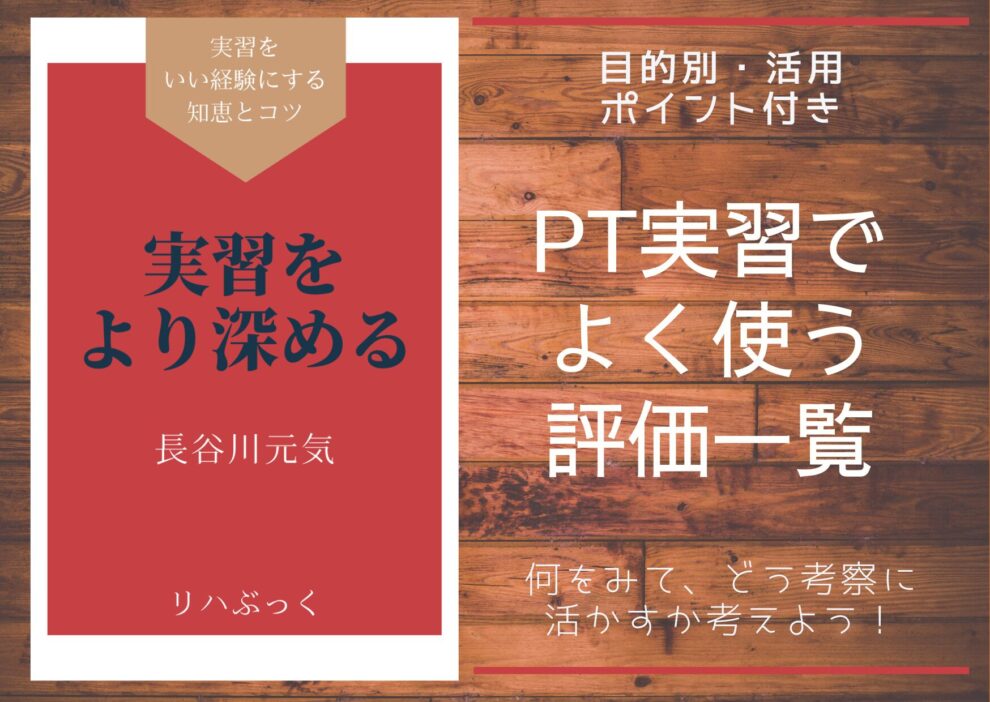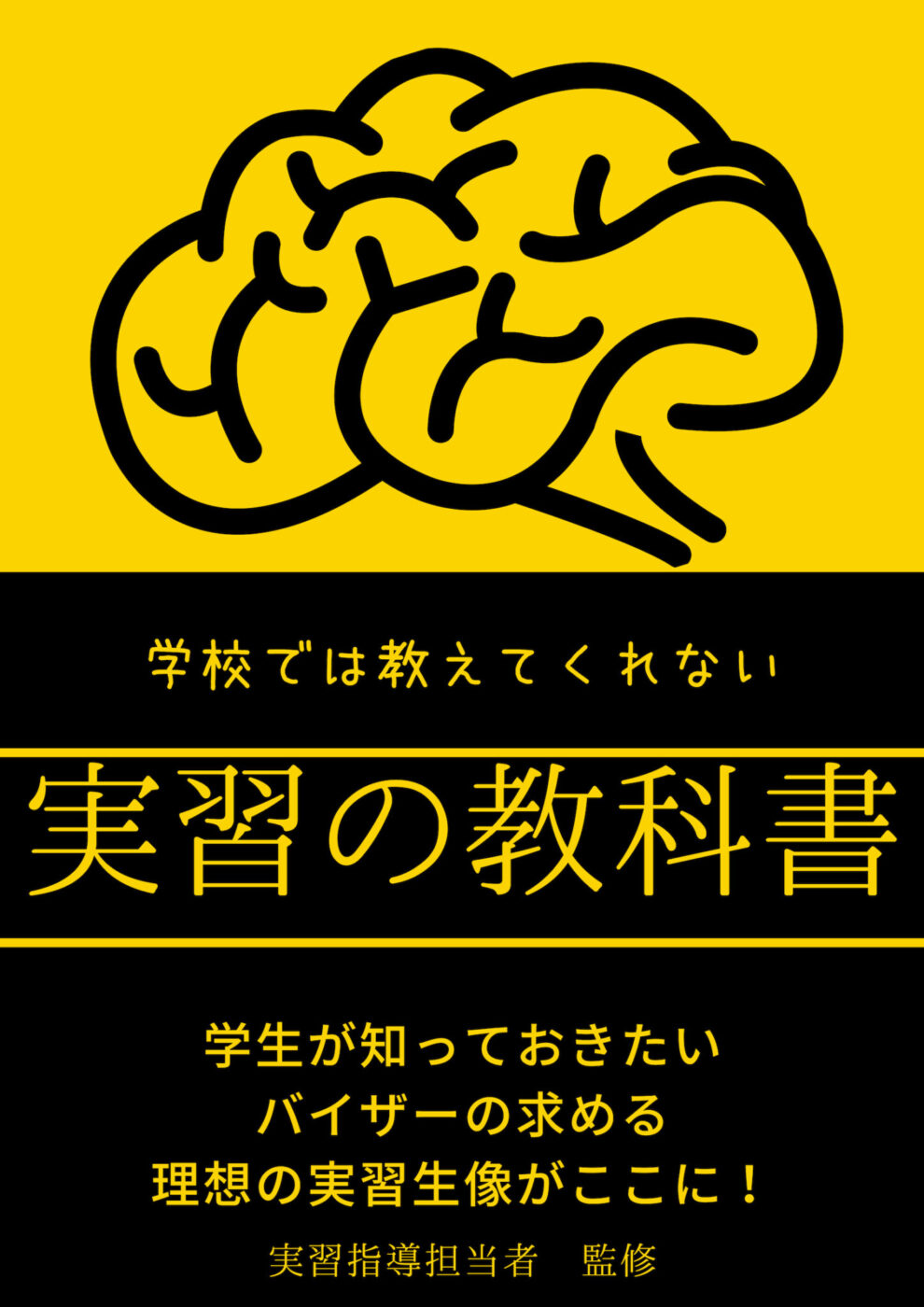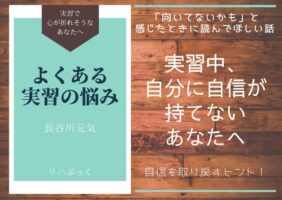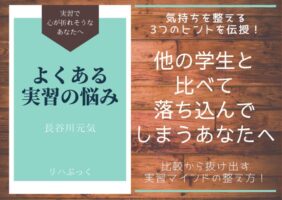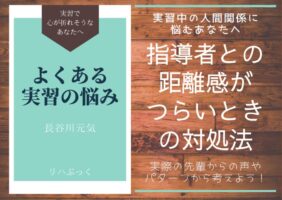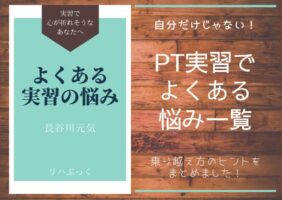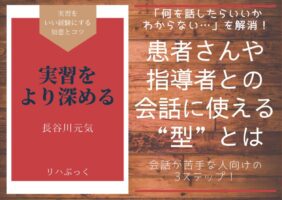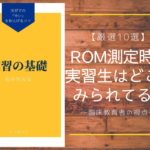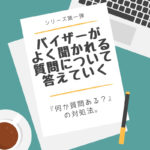「TUGとBBS、どっちを使えばいいの?」
「痛みの評価ってVASだけでいいの?」
そんな疑問、実習中によく出てきますよね。
この記事では、よく使う評価スケールを目的ごとに整理して、『何をみて、どう考察に活かすか』まで一緒に考えていきましょう!
この記事の目的
理学療法士の実習で頻繁に登場する評価スケールを、
「何を評価するのか」
「どんなときに使うのか」
「どう活かすのか」
という視点から整理。単なる丸暗記ではなく、“意味のある評価”となるようにしていきましょう!
目次
評価スケール一覧(目的別)
筋・関節機能の評価
■ 関節可動域(ROM)
- 何を評価?
→ 関節の動く範囲 - どう活かす?
→ ADL障害の要因が可動域制限にあるかを分析。
→ 治療目標の設定に活用。
角度だけ見ても意味は薄いです。
「エンドフィール」や「その可動域で生活にどんな支障があるのか?」がポイント!
■ MMT(徒手筋力テスト)
- 何を評価?
→ 筋力と左右差 - どう活かす?
→ 動作ができない原因が筋力低下にあるかを判断。
→ 訓練が必要な筋の部位を明確にできる。
ただの“3”ではなく、「なぜ3なのか」「どの筋で補っているのか」もみてみましょう。
さらに詳しく
実習中に私がよく伝えている”筋力”について触れた記事はこちら(外部リンク)
バランス・移動能力の評価
■ BBS(Berg Balance Scale)
- 何を評価?
→ 静的・動的なバランス能力 - どう活かす?
→ 高齢者の転倒リスクの評価に有効。
→ 移動の安全性や歩行補助具の必要性を考察する際に使用。
数値が低くても「どこで点数を落としているか」を見ると、転倒リスクの具体的な原因が見えてきます。
■ TUG(Timed Up and Go test)
- 何を評価?
→ 起立・歩行・方向転換などの総合的な移動能力 - どう活かす?
→ 移動の自立度・安全性のスクリーニング。
→ 動的バランスの低下をBBSや歩行能力などと組み合わせて実用的な移動能力を考察。
単なる秒数ではなく、「どの動作に時間がかかっているか」に着目することで、課題が見えてきます。
■ 歩行速度
- 何を評価?
→ 10m歩行などによる歩行スピード - どう活かす?
→ 自立度、転倒リスク、訓練効果の変化を見るためのベーシックな指標。
歩行速度は“結果”であって“原因”ではありません。
そうなった背景を読み取るためにも、TUGやBBSとの併用から安全性などを検討してみましょう。
■ SPPB(Short Physical Performance Battery)
- 何を評価?
→ 下肢機能(バランス、立位、歩行など) - どう活かす?
→ 身体機能の低下やフレイルの兆候を把握
→高齢者の転倒・要介護リスクを多面的に評価し、予防介入の根拠に。
点数に表れにくい「立ち上がり方」や「ふらつき」にも重要なヒントがあります。
ADL・自立度の評価
■ FIM(機能的自立度評価)
- 何を評価?
→ 食事・更衣・排泄・移動などの日常生活動作の自立度 - どう活かす?
→ 入院時や退院判断時の生活自立度の指標に。介助量や退院先の判断材料にも。
同じ“要介助”でも「どの場面で、なぜ介助が必要なのか」によって解釈が変わります。
■ Barthel Index
- 何を評価?
→ 基本的なADL能力(食事・整容・移乗など) - どう活かす?
→生活上の介助量を数値化。
→ リハビリの経過や、施設入所・在宅復帰の判定材料として。
点数は同じでも、その背景にある“生活の難しさ”は人によって違います。
痛みの評価
■ VAS/NRS(痛みスケール)
- 何を評価?
→ 痛みの主観的な強さを数値化(0〜10) - どう活かす?
→ 疼痛の程度や変化を定量化し、訓練強度や効果判定に反映。
数字以外にも、安静時痛・動作時痛など「どんなときに、どう痛いか」まで言語化して初めて意味を持ちます。
■ ペインマップ(痛みの部位図)
- 何を評価?
→ 痛みの部位・広がり・左右差 - どう活かす?
→ 筋・関節・神経など痛みの由来を視覚的に整理できる。
視覚的に情報を整理して、評価や治療戦略に活用していきましょう。
麻痺の評価
■ Brunnstrom Stage
- 何を評価?
→ 脳卒中後の麻痺の回復段階(Ⅰ〜Ⅵ) - どう活かす?
→ 麻痺の現在地と今後の回復予測を立てるのに使える。
→機能レベルに合わせた訓練の段階づけにも。
同じステージでも、動き方や随意性を見ることで回復段階をより正確に掴めます。
■ SIAS(Stroke Impairment Assessment Set)
- 何を評価?
→ 脳卒中後の運動・感覚障害の程度 - どう活かす?
→ Brunnstromと合わせて多角的に片麻痺を評価できる。
SIASは数字の羅列ではなく“全体像”を見るためのツール。
麻痺がある/ない だけではなく、感覚障害や協調性とのつながりを見抜きましょう。
疲れの評価
■ Borgスケール(主観的運動強度)
- 何を評価?
→ 疲労感、運動強度の主観的な負担を数値で可視化 - どう活かす?
→ 呼吸器疾患や高齢者における無理のない訓練負荷調整に。
同じ「13」でも、表情や話し方でその“本当のしんどさ”は変わってきます。
■ FSS(Fatigue Severity Scale)
- 何を評価?
→ 慢性的な疲労が生活に与えている影響 - どう活かす?
→ 疲労が日常生活をどれほど制限しているかを把握できる。
慢性疲労は見えにくい。でも、“行動の変化”がヒントになることが多いです。
その他の重要な評価
■ バイタルサイン(血圧、脈拍、SpO₂、呼吸数など)
- 何を評価?
→ 生命兆候・運動の安全性 - どう活かす?
→ 運動可否の判断、体調急変の兆候の確認に必須。
→訓練リスクの把握を。
それぞれの数値は、ただの数値ではなく、”運動中にどう変化するか”を見るのがカギです。
さらに詳しく
■ 姿勢評価
- 何を評価?
→ 骨格の配列・アライメント・重心の位置 - どう活かす?
→ 姿勢由来の疼痛や動作障害の原因を可視化する。
“姿勢の癖”が、そのまま動作障害の鍵になることも。
第一印象から見抜ける力をつけていきましょう!
さらに詳しく
私がよく実習生さんに伝えている”良い姿勢”について触れた記事はこちら(外部リンク)
■ 動作分析
- 何を評価?
→ 起き上がり・立ち上がり・歩行などの動作パターン - どう活かす?
→ 非効率な動作・代償動作の特定
→ リハビリの優先課題を明確にできる。
動作分析は「観察力 × 仮説力」。
パターンを見て考える習慣を身につけよう。
さらに詳しく
実習生でもできるシンプルな歩行分析のやり方についてはこちら(外部リンク)
■ 栄養・排泄評価(体重、食事摂取量、排尿・排便)
- 何を評価?
→ 栄養状態、全身状態 - どう活かす?
→ サルコペニア・褥瘡リスクの把握や、訓練の継続可能性の判断に直結。
食事量の低下や排泄の変化は、回復の阻害因子としての“サイン”。
見逃すとリスクが広がります。
さらに詳しく
これまで触れた項目の中には、その項目において実習中に知っておきたい知識について触れた有料noteのリンクを貼っておきました。
臨床でもよく使う知識ですので、そちらも参考にしてみてください。
さいごに:実習で評価を“意味のあるもの”にするコツ
単に数値を書くのではなく、
「なぜこのスコアなのか?」
「どう臨床に関係するか?」
まで考えることが大切です。
評価は“ゴール”ではなく“仮説の入口”なのです。
学生さんは、この記事を何度も読んで、評価→考察→介入のつながりをより意識してみましょう!
〜〜Plus〜〜
歩行分析をシンプルに行うコツはこちら(外部リンク)
Next>>
見学中に何をみて良いのかわからないという方はこちらの記事へ
<<Back
理学療法士学生のための技術大全はこちら