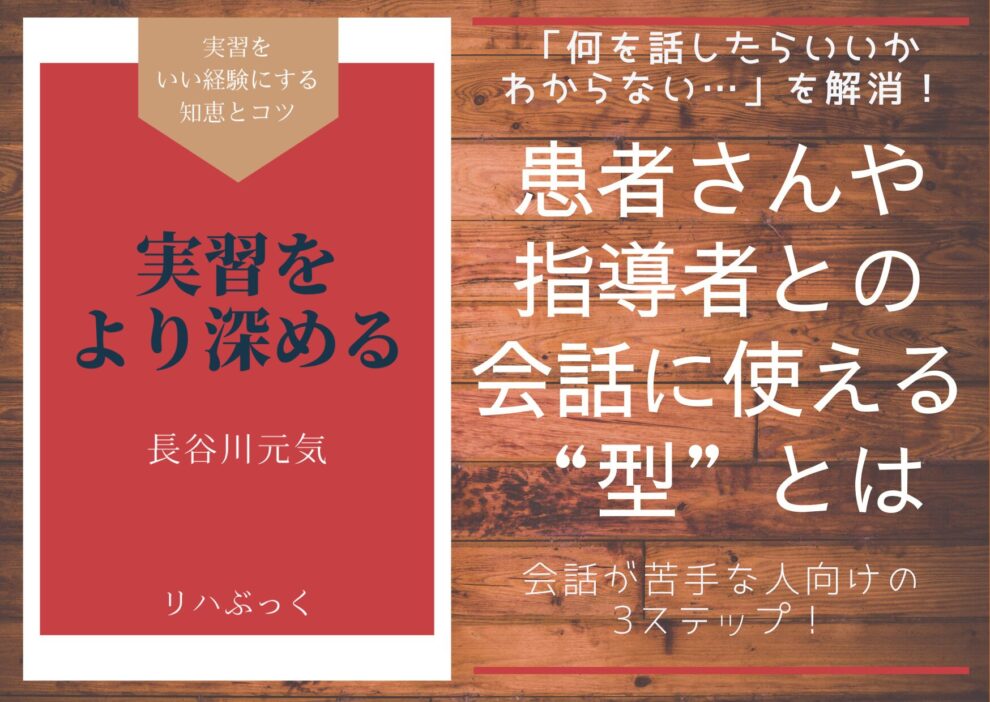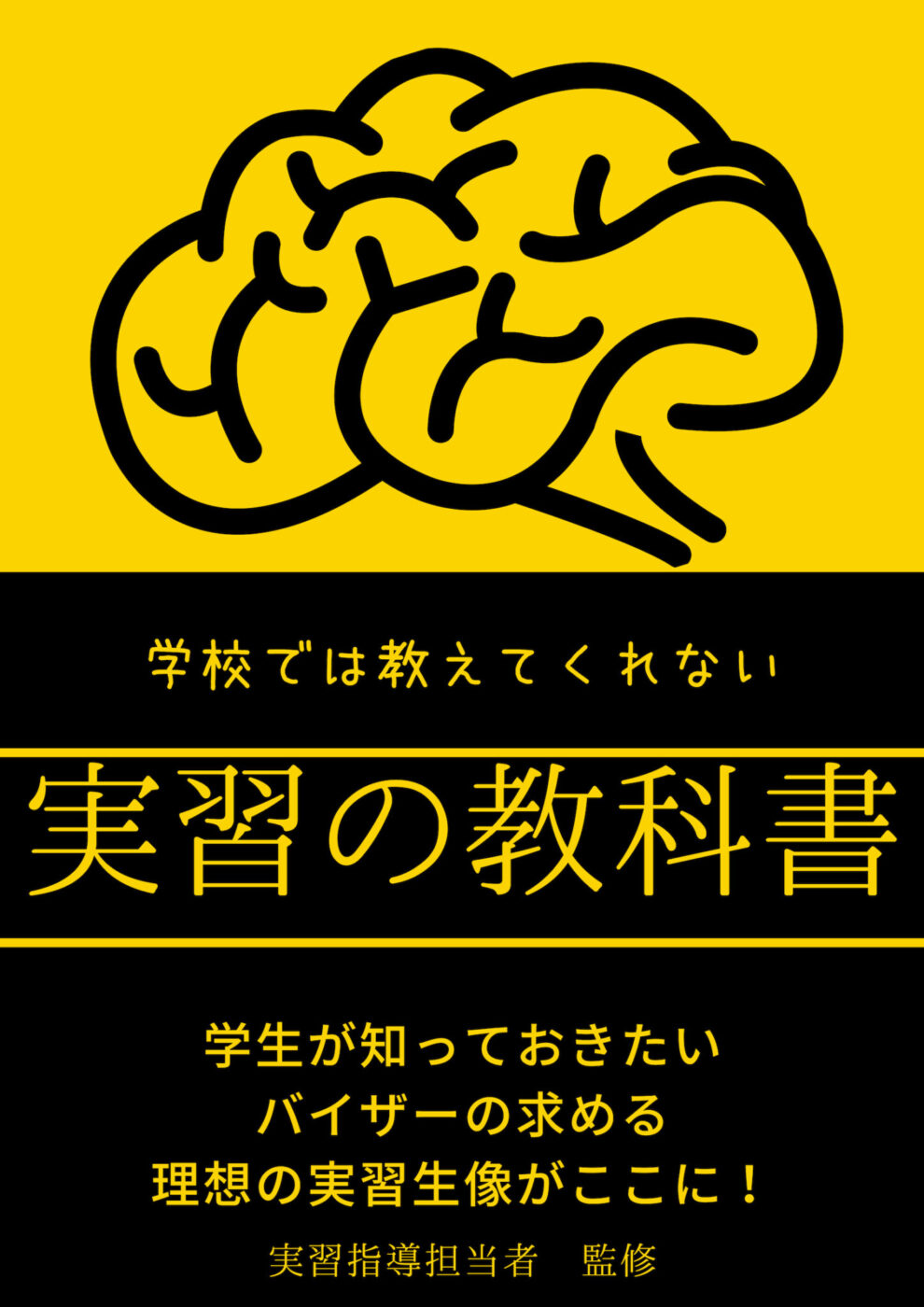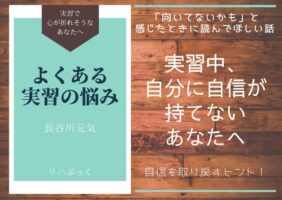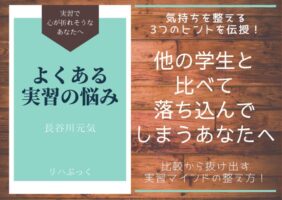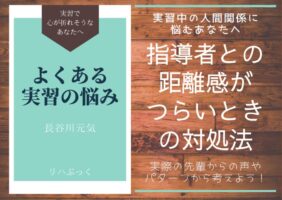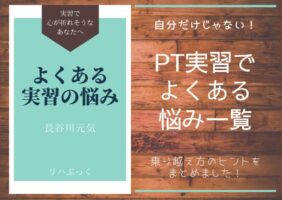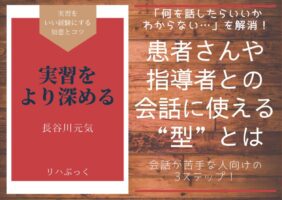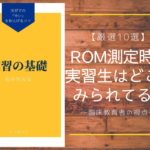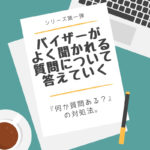「患者さんとの会話がうまく続かない」
「何を聞けばいいのかわからない」
初めての実習でも、何度目の実習でも、こんな悩みを抱える学生は少なくありません。
そして、その会話が苦手な学生ほど、話題をゼロから作ろうとしがち。

ですが、実習中の会話には“型”があり、コツを押さえれば誰でも会話に困ることが少なくなります。
”型”を知り、患者さんや指導者との会話がスムーズなものにして、たくさんの学びを得ていきましょう!
この記事の目的
実習中、患者さんとの会話が緊張してしまう理学療法士学生に向けて、自然なコミュニケーションを築くための3ステップを紹介します。
「何を話せばいいかわからない…」という不安を和らげて、患者さんと安心感のある会話ができるようにしていきましょう。
目次
患者さんとの会話が苦手な人向け「3ステップ」
会話が苦手でも大丈夫です。
ただでさえ緊張する実習ですから、最初からうまく話せなくて当然なのです。
そういう時こそ、“うまく話す”より“誠実に聴く”が正解。
そのための3ステップを用意しました。

STEP1|安心感を与える「第一声」を用意する(名乗る・目的を伝える)
患者さんは、学生の緊張を敏感に感じ取ります。
最初の一言は、難しい言葉を使うよりも、「目線・声のトーン・笑顔」で柔らかさを出すことが大切です。
- 「おはようございます。今日は天気がいいですね。」
- 「理学療法士の学生の◯◯と申します。今日は〇〇の様子をみせていただいてもよろしいでしょうか?」
- 「寒くないですか?体調は大丈夫ですか?」
こうした短い挨拶は、場を和ませる“潤滑油”になります。
「学生ですが、えっと、今日は…(目的が曖昧・自信なさげ)」
これではNGです!
STEP2|聴く(傾聴・確認)
「どうですか?」という抽象的な質問は答えづらいものです。
代わりに、選択肢を提示する質問が有効です。
- オープンクエスチョン:「最近、歩いているときに困ることはありますか?」
- クローズドクエスチョン:「階段をのぼる時、痛みはありますか?(はい/いいえ)」
- 確認(リフレーズ):「つまり、朝が一番つらいということですね?」
会話で困る実習生さんの多くは、Yes/Noのクローズドクエスチョンを多用している傾向にあります。
しかし、このクローズドクエスチョンは、会話のネタ数によってはあまり長く会話が続かないことがあるので、ご注意を。
オープンとクローズドの両方を使いながら、相手から言葉を引き出すようにしてみましょう。
そうすると、意外な話の展開にもなり、会話に花が咲くことでしょう。
この記事の冒頭に書いた“うまく話す”より“誠実に聴く”が正解というのはそういうことです。
ちなみに、“沈黙=悪”ではありません。
「待つ勇気」もコミュニケーション能力です。
さらに詳しく
誠実に聴くためのコツを知りたい方はこちら(外部リンク)
STEP3|広げる(要約・共感・次へつなぐ)
会話を広げたいときは、患者さんの答えをオウム返しすることも大事な会話術。
共感するだけでも安心感が生まれます。
- 要約:「今のお話をまとめると、痛みは朝が強くて、午後になると少し楽になるのですね。」
- 共感:「それは不安でしたよね。」
- 次へ:「その点をふまえて、今日は〇〇を一緒に確認させてください。」
この3ステップを、毎回同じ順でやってみましょう。
それだけで会話が続いて、長い沈黙や微妙な時間が流れることが少なくなるはずです。
すると、不思議なことに“落ち着いて見える学生”になれているでしょう。

会話を記録し”次に活かす”
患者さんとの何気ない会話から気づくことは、次回の関わりに生かせるヒントの宝庫です。
気づいたことはメモ帳に短く書き残しましょう。
- 膝の痛みは朝が特に強い
- 孫の話題になると笑顔になる
こういったことを次の会話の時にも覚えておけば、親密さがグッと深まります。
また、これらはSOAP記録のS(主観)にもつながり、評価や計画立案の材料になるのです。
「会話は準備が9割」と言われるくらい準備が大切なもの。
少しずつ会話の引き出しを増やしていきましょう。
よくある困りごと別「言い返し方・対応例」集
“言い返し方”=反論ではなく、状況を整理し、前へ進むための言葉の型です。
実習でよくある困ったシーン別に“即使える”フレーズを持っておきましょう。
指導者に鋭く問われたとき(例:「なんでそれ選んだの?」)
- 「理由は2つあります。1つは〜、もう1つは〜です」
(即答できない場合) - 「仮説はありますが、根拠が薄いので、再度確認して明日お伝えします」
「それ、考察になってないよ」
- 「SとOのつながりを明確にできていませんでした。Oに◯◯を追加し、Aでは△△の観点から整理し直します」
忙しそうな指導者に質問したい
- 「◯◯について5分だけお時間いただけますか?3つ確認したいことがあり、要点だけまとめました」
→“時間を区切る” + “数を示す” で、聞かれる側のストレスを最小化へ。
認知症の患者さんへの会話で困る
- 「◯◯さん、今から□□をしますね。終わったら△△しましょう」(“短く・具体的に・視覚で支援”)
- 否定しすぎず、話を受け止めた上で安全に誘導:「そうなんですね。では、ここに座ってから続きをお聞きしてもいいですか?」
質問に答えられなかった
- 「分からなかったので、◯◯と△△を照らし合わせて整理して、明日までに提出します」
“守りの言葉”ではなく“前に進む言葉”を持っておきましょう。
すぐに言い切れないなら、「明日までに答えを出す」が最強の誠実さとなります。
まとめ:会話や対応は“センス”ではなく“型”で伸びる
- 会話は準備が9割!
- 患者さんには「用意する→聴く→広げる」
- 指導者の言葉は「What / Why / How / Next」で再現可能なメモに
- 困りごとには“前へ進むフレーズ”を準備しておく
会話や対応は、練習すれば確実に伸びる“技術”です。
この記事をブックマークして、困ったときの“辞書”として使ってくださいね。
〜〜Plus〜〜
実習で身につけたい”聴く力”について解説した記事はこちら(外部リンク)
Next>>
SOAPの基礎を知りたい方はこちら
<<Back
実習中に使う技術をまとめた記事はこちら